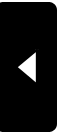スポンサーサイト
100均素材で撮影ボックス 背景紙編
2019年02月05日

100均素材で撮影ボックス、光を拡散させる半透明のボックスは棚板3枚とジョイントで完成。
背景紙は単色の大きめの色付紙でも良いのですが、細長く、しっかりと強度があって落ち着いた柄もあるリメイクシートなるものを発見。柄面の裏が粘着シートになっている壁紙です。100均やホームセンターで入手できます。

丸めて陳列してあるのと剥離紙の関係で紙にクセがついていたり、シワになりやすいので、大きめの厚紙に貼り直します。
実はここでシワ無くキチンと貼るのが最大の難所で、コツは一気に貼ろうとせず、片方から空気を抜きながらゆっくりと貼ることです。
貼り終えたらボックスの背面側にクリップやテープで固定、底面と背景面の境が曖昧になるようにゆるやかなカーブを描くように敷いてやれば完璧です。

あくまで背景なので、自己主張せず、それでいて被写体を引き立ててくれる柄を探してみましょう。
参考に、今までの黒単色。

大理石風、黒。好みだけど艶ありなので使いづらい。

英字新聞風。

僕はホームセンターで見つけた大理石調がお気に入りです。

100均素材で照明ボックス
2018年12月04日



模型が趣味で写真も好きで、息子が生まれた頃に初めてデジカメを買ったのでそろそろ20年近く色々と撮ってきた事になります。
霧島食育研究会の活動で本格的に料理写真を撮るようになり、そこで物撮りの基本を勉強しました。
最近は鹿児島モデラーズコンベンションに参加するようになり、模型の撮影も増えてきました。一生懸命組み立てた模型も、経年劣化は避けられず、塗装が退色したり、部品が破損したり。
なので完成した模型をきちんと写真で記録して残すのは、大事な事だと思います。
模型などの物撮りのポイントはカメラの性能よりも照明と背景です。
そんな時にネットで見かけた撮影ボックス、早速真似して使ってみたら、これがいい感じ。
100円ショップダイソーの自作棚のコーナーにあるワイヤーラック、その中にワイヤーではなく半透明シートの棚板があります。これが小型の照明ボックスに最適な大きさで、左右と上側のシート3枚と接続用のジョイントも合わせて500円未満で購入できて、組み立ても1分程度。
背景紙も文具店などで厚めで広めの色紙をボックスの大きさに合わせて切り出してテープで貼っただけです。
物撮りの照明の基本は点光源ではなく、面光源。
要するに光源・照明の発行面積を広げて、柔らかい光で被写体を包む事です。
照明ボックスの左右からLEDライトでライティングすると、半透明シートで一度光が拡散され、発行面積も広がり、被写体を包むように光が回るようになるわけです。
照明は市販されているLEDライトや蛍光灯ライトで十分です。この時気をつけなければならないのが、同じ種類のライトを使う事です。人の目には同じに見えても、光源の種類が違うと色を正確に再現するのが難しくなります。
白熱電球だと熱を持ちすぎて危険だからやめましょう。
背景紙は黒が一番使いやすいようです。100円ショップでもいろんな紙が売っていますが、ペラペラの紙だと折り目が付きやすく、使いにくいので、多少厚みがあった紙を用意した方が良いようです。床と背景がくっきりしないように緩やかなカーブで設置しましょう。
レフ板も紙でもできますが、100円ショップの白のカラーボードを適当な大きさに切って、二枚をテープで繋いでやると使い勝手の良いミニレフ板が完成です。
レフ板は実際に被写体に向けて光が十分に回らない部分を探しながら、角度を調整してやると良いです。
撮影時は広角側だと遠近感が強調されて、被写体が歪んで写ってしまうことがあるので、多少ズームします。この時、背景紙の外側が写り込まないように気をつけましょう。
ポイントを整理します。
物撮りはカメラにお金をかけるより、照明まわりから。
点光源ではなく面光源で。
背景は極力シンプルに。
小型レフ板で陰を起こす。
この100均照明ボックスは霧島市国分のマルタカ屋模型店さんに置かせてもらっています。評判も上々です。
撮影のモデルはモデコン仲間のくぼっちゃさんのMG1/100GMでした。
模型の撮影に興味がある方の参考になれば幸いです。
篠原重工98式AVイングラム
ランナースタンド作ってみた
2017年09月28日

ランナーが多いキットは、スペースもとるし、必要なランナーを探すのに手間取ったり。
そんなある日、ランナーを立てて置くことで省スペースになる便利ツール、ランナースタンドなるものの存在を知ることに。
これは良いなと思う一方で、これくらいなら自作できそうと思い立つ。
お馴染みのホームセンターであれこれ探してみたら、ちょうど良い感じの素材が。

溝付角材。
縦横24ミリの角材の一辺に数ミリ幅の溝が掘ってある。
溝の深さが10ミリほどあるので、そこにランナーを差し込む感じ。



長さが91センチあるので、15センチで切断、安いホビーノコギリで簡単に切れました。
切断面は紙ヤスリで慣らして、6本確保できるので、これを木工用ボンドで接着するだけ。
適度な重さでグラつかないし、木材の柔らかさでパーツを痛めることもないし、ちょうど良い溝の深さです。
使い勝手としては、標準的なHGのキットがランナー3枚程度なので、3本で1ブロックが省スペースでいい感じ。
ネットで検索すると、ランナースタンド自体が幅をとるものを見かけるが、これだと、横幅72ミリ。
ランナーの枚数が多い時は、ブロックごと増やしていけば良い。
溝の幅も数種類あるのですが、幅3ミリだと少し狭い感じで、幅4ミリが使いやすいです。

HGのGエグゼスだとランナー3枚なのでこんな感じ。
一番上の写真はミニプラガリアン、鉄巨神。
材料費は約250円。
安価ですし、加工も簡単で効果抜群です。
展示台座作ってみた その2
2017年09月04日

1/144サイズHGガンプラ用の展示台座作りの続き。
最近のHGシリーズはほとんどがアクションベース対応で設計されているので、その受け軸を利用して展示用台座をお安く作ってしまおうという企画。
台座部分はMDF材でピッタリなのを発見。
支柱を3ミリプラ棒でやってみたら強度的に厳しかったので、再び100円ショップで素材探し。

使えそうな素材を三つ購入。

園芸コーナーで見つけた洋蘭支柱、真ん中に鋼線が通っていて周りを緑色のビニール樹脂でコーティングしてあります。
芯が硬く重い 。3ミリ穴にもピッタリでいい感じ。

緑色が気になったので、ラッカー系のつや消し黒吹いたらこんな感じ。
45センチ10本入りなので9センチで換算したら50本分、単価は約2円。
ただ、芯に通っている鋼線がとても硬く、針金用のニッパーでは切断は無理。小型のワイヤーカッター程度は必要です。

竹ヒゴ3ミリ径。
とにかく軽くて加工も簡単。
普通の家庭用のカッターで切断も可能。
ですが3ミリ径には少し太い感じで、3ミリ穴にはギリギリか、個体差によっては入らないことも。まあカッターで簡単に削って径を 調整できます。

そのまま使うとかなり天然素材感があるので、油性マジックで黒く塗ってやるといい感じ。
強度的にも問題なく、36センチ20本入りなので9センチ換算80本分、単価は1.35円。

アルミ自在ワイヤー3ミリ径ブラウン。
実際に3ミリ穴に差し込んでみるとかなり細い感じ。
台座にも軸受けにも隙間があるので、写真のジェノアス、よく見ると少し傾いてます。
アルミの先端部にテープ類などを巻き付けて径を太くしてやるとキッチリ収まります。
強度も問題なく、色もブラウンで落ち着いているし、金属のツヤもあるので展示用にはいい感じ。
ただ、巻いてある状態で購入するので真っ直ぐに伸ばす作業が必要です。
僕はある程度曲がりを修正してから、作業用のマットと台座用のMDFで挟んでゴロゴロしました。肉眼ではまっすぐだとおもいます。
210センチなので9センチ換算23本、単価は4.7円。
それぞれ一長一短ありますが、個人的には洋蘭支柱が使いやすい印象。
ペンチを使えば鋼線を曲げて角度をつけることも可能です。
切断にはワイヤーカッターが必要ですが、ダイソーで300円で販売している商品もあるらしいです。
黒く塗る一手間が必要ですが、一個あたりの材料費は約20円程度、ご参考に。
展示台座作ってみた
2017年09月01日

鹿児島モデコンに出品するようになり、展示する際の見せ方や、模型の安定した設営に気をつけるようになりました。
特にガンプラは人型ですので、重心が高く不安定になりがちで、背中にでかい装備を背負ったキットだとやはり台座に固定した方が安心です。
メーカーから専用の台座も販売されていますが、今回、HGキット用のディスプレイベースを自作してみました。
いつものように100円ショップで使えそうな材料を物色。

台座用にはMDF材と呼ばれる木材を接着剤で固めた素材でお手頃なのがありました。
10センチ四方で標準的なHGを展示するにはちょうど良い広さで、厚さも6ミリ、適度な自重と硬さもあり、木材なので加工も簡単です。
6枚入りで税込108円なので一枚あたり18円の安さです。
支柱の接続部には3ミリのプラ棒を使うので、100円ショップで見つけた3ミリ径のミニドリルでベースとなるMDF材の真ん中に穴を開けます。
3ミリプラ棒を8センチで切断、ベースに開けた穴に差し込みこれで完成。

HGジェノアスだとこんな感じ。
ただ、3ミリプラ棒だと標準的なHGのモデルの重さでも不安定な感じ。結構グラグラで、何かのアクシデントで折れてしまいそう。
白色も自己主張が強いかなあ。
なので支柱となる素材を探しに再び100円ショップへ。
つづく。
ガンヘッド
2016年03月25日



人生初の壽屋インジェクションキットは、ゾイドではなくガンヘッド。
特に改造はせず、ストレート組み。ポイントでセンサー部にビーズアクセサリー用のラインストーン。
派手さのないキットなのでアクセントになります。
懐かしい映画ですが、今見ても良いデザインですねえ。
時代に対して早過ぎた映画というか、いろんな意味でもったいない映画。
キットは結構なボリューム。
現在は国分中央のマルタカ屋模型店に置かせてもらっています。
モデコンにも持って行こう。
道楽日記の始まりです
2013年07月22日

子供のころアニメ機動戦士ガンダムが大ヒットし、同時にガンプラも大ヒットしました。日曜の朝に新作キットを求めておもちゃ屋の前に並び、欲しいキットを求めて、自転車で隣町の文房具屋を巡回した世代です。
社会人になり、親となり、段々模型からも離れていましたが、鹿児島市の黎明館で毎年開催されている模型展示会「モデラーズ・コンベンション」を観にいき、完全に模型熱が再燃してしまいました。
それにしても最近のガンプラって凄い進化ですね。
接着剤は要らないし、部品が色分けされているし、プロポーションはかっこいいし、関節は良く曲がるし。
いつか作ろうと、買ったけどそのまま押入れで熟成させていたガンプラたち、40歳を過ぎて再び楽しんでいます。
そんな道楽日記の始まりです。